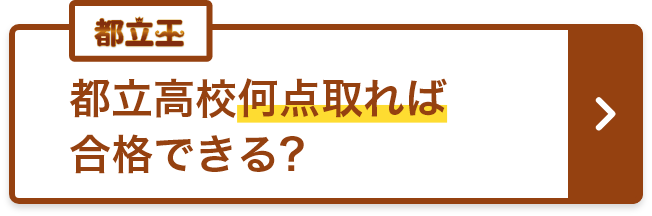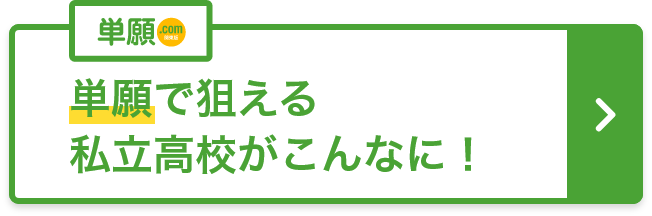今回から地域別に都立高入試状況(おもに普通科高校の一般入試状況)を見ていくことにします。
千代田区・港区・品川区・大田区

この地域全体の応募者数は2,606人で前年度より124人、4.5%の減でした。これはこれから見ていく地域区分の中では最も少ない減少率です。前年度に296人9.8%の大幅減になっていることや、地元中心の入試になる人気校が多いため、今回の私立志向の影響が最小限に抑えられたのかもしれません。
日比谷は前年度に大幅な応募減となり、緩やかな入試になりましたが、今年度はその反動で応募増。倍率も上がりました。実質倍率もやや上がって1.46倍になり、不合格者は124人と前年度より38人増加しています。しかし、150~200人程度の不合格者を出していた時期にくらべるとまだ少ない方なので、本来の入試状況に戻ったとは言えません。ただ、今回の私立志向の高まりによる影響はさほど受けずに済んだようです。今春の東大合格者は80人を超え話題になりました。来春はさらに多くの応募者が集まるでしょう。
小山台も前年度の応募減の反動で40人増え1.4倍台に上がりました。しかし、コロナ前の2020年度以前までは男女合わせて400人を超える応募者がいたことから、今年度の368人という人数も本校としては少ない方になります。ただこの5年間でみると標準的な応募者数なので、今年度は私立志向の影響はほとんど受けなかったといえるでしょう。
三田は男女別募集から男女合同募集の影響を受けた1校です。男女別募集を実施していた2023年度以前は男女合わせて400人以上の応募者を集めていましたが、男女合同募集になった2024年度は393人。今年度はさらに減って354人までになりました。不合格者数は119人で前年度より32人減り、近年でもっとも緩やかな入試になりました。元々人気の高い学校だけに来春はこれ以上の応募減は考えられず、倍率アップの可能性が大きいと思われます。
雪谷は応募締め切り時は364人で前年度の369人とそれほど変わりませんでしたが、志願変更で田園調布との間で出入りがあったのか、最終応募者数は前年度より22人の減となり倍率も下がりました。その結果、実質倍率1.42倍、不合格者数は95人で3年ぶりに100人を切り、雪谷にしては緩やかな入試だったといえるでしょう。
田園調布は私立志向の影響を受けたことがよくわかる入試になりました。応募者数は前年度より66人の大幅減。300人を切ったのは7年ぶりのことです。応募者が減ったのにもかかわらず棄権率も前年度(11.1%)より若干アップしました。併願校としてよく利用される東京や駒場学園の推薦応募者が増えていることから、これらの私立高に移動したと考えられます。なお来春の入試では全日制の分割募集が廃止されるので、本校の一般第一次募集の募集数は学級減がなければ増加する見込みです。(今年度の分割後期募集の募集人員は12人でした)
大崎の応募者数は前年度(336人)とほぼ同じで、この3年間330人台と安定しています。入学生は大田区からの生徒で6割程度、品川区から2割程度でこの2地区で全体の8割を占めています。今年度、大田区の生徒数が140人ほど減りましたが、それでも前年度並みの応募数を確保し根強い人気があることを示しました。難関大学に一般入試で現役進学することを目指した特進クラスを設置するなど、進路指導に熱心で大学進学実績も伸びているようです。
八潮の応募者数128人は最近の5年間でもっとも少なく、しかも分割後期募集人員を40人から20人に半減し、その分を前期に上乗せしたことで0.76倍に下がりました。応募者数は2023、2024年度と増加(2022年度より137→154→173人)し、2024年度の倍率は1.17倍と本校としてはかなり高い倍率になったことから、その反動による応募減ともいえますが私立志向がそれに拍車をかけた形です。来春は全日制の分割募集が廃止されるため、学級減がなければ一般第一次募集の募集人員は増加する見込みです。
大森の応募者数は2022年度より153→77→69→58人と減少傾向です。特に2023年度は蒲田や八潮に移動したのか半減しました。今年度は募集学級減での募集でしたが、それでも応募者数は募集人員の半数に達しませんでした。これは私立志向というより通信制志向の高まりによる低倍率と考えられます。
蒲田は応募者数の増減の激しい学校です。2020年度より114→72→96→133→92→93人と推移し急激に増えたり減ったりします。通信制高校と本校との間で受験生の行き来があるのかもしれません。しかし、今年度は前年度並みの応募者数で倍率もほとんど変わらず珍しく安定しました。エンカレッジスクールとして入学者選抜では学力検査を行わないことや授業時間が30分と短いこと、体験を重視した学習など特徴も多いことから、下げ止まっているのかもしれません。
美原は大田区の生徒減と私立志向の高まりにより応募減となり、4年ぶりに定員割れになりました。コロナ禍以前は200人を超える応募者を集めていましたが、2021年度に155人に落ち込みました。2022、2023年度と増加が続いたものの、2024年度に減少に転じ、そして今年度はさらに減少するという流れです。学年制普通科高校が男女別募集から男女合同募集となり、本校のような単位制普通科と同じ選抜方法になったことも影響しているのかもしれません。
新宿区・渋谷区・目黒区・世田谷区

この地域全体の応募者数は前年度より265人6.4%減りました。これは他地域と比べると少ない方です。東京都の中心部に位置しており、しかも私立志向の高い地域にもかかわらず、これだけの減少率で済んだのは、人気校が多いことや隔年現象による応募増の学校があったことが要因になっていると考えられます。不合格者数は261人減の1,044人で応募減の分、緩和された形です。
戸山は27人の応募増となり526人と3年前までの水準に戻り、倍率も2倍を超え、本来の応募状況に戻りました。受検棄権率も前年度の19.6%から16.5%に下がり、本校第一志望者が増加したことを示しました。国立大学医学部を目指すチームメディカルが特色のひとつで、昨春の実績が現役10人と2桁に乗せたことが評価されたのかもしれません。
一方で青山は25人の応募減となり倍率も2倍を切りました。本校が一般募集人員の倍以上の応募数を集められなかったのは7年ぶりのことです。また受検棄権率も前年度の10.0%から12.0%にややアップしており、私立志向の影響を受けた選抜状況になったといえるでしょう。昨春の国公立大学の合格実績が3年ぶりに現役100人を超え実績は上がっています。また学校行事や部活動も活発であることから、来春の入試では応募増になる可能性が高いと予想されます。
駒場は2023、2024年度と2年続いた8学級募集から元の7学級募集に戻った結果、応募者数は37人の減になったものの、倍率は前年度(1.83倍)より上がりました。私立志向の高まりにより応募減になったものの、423人は本校としては多い方なので、一定の人気は維持しているものと考えられます。通学の便もよく町田市や調布市、三鷹市などの多摩地域からも受けに来ており、幅広い範囲から受検生が集まります。
目黒は今年度私立志向の影響を強く受けた学校のひとつです。応募者数は前年度より106人、約3割の減となり倍率も1.40倍に下がりました。応募者数が200人台にとどまったのは最近の5年間ではありません。人気校で応募者が募集人員の倍以上集まる年も多く激戦が続いていましたが、今年度の私立志向がきっかけになって大幅な減少に結び付いたのかもしれません。
広尾も人気校のひとつで、前年度の倍率は2.16倍で受検生の4割以上が不合格になる激戦でした。今年度は応募者数が8人減で留まりましたが、募集学級数が1学級増の6学級募集になったことから倍率は下がり、本校としては緩やかな入試になりました。立地の良さから幅広い範囲から受検しにくることと、学級増により私立志向の影響をさほど受けなかったと思われます。来春は元の5学級募集に戻る可能性があるので要注意です。
松原は前年度に不合格者1人のみという緩やかな入試になったことから、今年度は応募者が54人の増となり倍率も1.40倍にアップしました。ところが受検棄権者が前年度(8人)の3倍以上の27人に増えたことから受検者数は192人に減り、倍率も1.23倍に下がりました。受検者数が200人を切ったのは最近の5年間で前年度に次いで2回目です。今年度は応募者は増えたものの、私立志向の影響を受けた形です。
桜町は2022年度からの応募者数が275→316→271→290人と、増えたり減ったりする隔年現象があります。今年度は増加の年で倍率も前年度の1.08倍から1.15倍にアップしました。しかし受検棄権者が増加(21→28人)したことから受検倍率は1.04倍に下がり、しかも入学辞退者を多く見積もったのか、水増し合格者を6人とったため不合格者は4人で留まり緩やかな入試が続くことになりました。やはり私立志向の影響を受けてのことと思われます。
千歳丘は変動が激しく、2022年度(1.02倍)、2023年度(1.06倍)と2年連続で1.0倍台の低めの倍率が続いたものの、翌2024年度は応募者が一気に59人増加し1.3倍台に上がりました。そして今年度はその反動が起こり、43人の応募減となって倍率も1.14倍に下がっています。従って、今年度の応募減は私立志向によるものというより、前年度の反動があったといっていいのですが、受検棄権率が前年度と同じ7.5%と高い水準を維持したところに私立志向を窺わせる動きがみられました。
深沢は通信制志向の高まりによる影響を受けている学校といえます。2020年度より応募者数が募集人員を上回ったことはありません。今年度も応募倍率は前年度と同じ0.87倍で留まりました。そしてさらに受検棄権者が増加(12→19人)し、棄権率が9.7→15.4%にアップしたことから、私立志向の影響も受けたようです。分割募集実施校で当初の分割後期募集数は16人でしたが、前期で39人の欠員が生じ、後期の募集数は55人に増えました。なお、2026年度より生徒の多様性に対応した教育体制をもつ新しいタイプの高校に再編される予定です。
新宿は私立志向の影響を強く受けた学校といっていいでしょう。応募者数は135人減で倍率も1倍台で留まりました。コロナ禍の2021年度入試でも応募者が545人で倍率1.92倍にダウンしているので、その時と同じ衝撃を受けたことになります。それでも不合格者数は200人で受検者数の約4割に該当しますが、本校としては緩やかな入試でした。しかし人気校だけに来春の入試では応募増になる可能性が高いでしょう。
芦花は人気校のひとつで、今年度も私立志向の影響はほとんど受けず、2年連続で応募倍率が2倍を超えました。ただ受検棄権者は4人増の9.4%で前年度(8.4%)よりややアップ。棄権率はこの5年間6.1→6.6→5.8→8.4→9.4%で上昇傾向で、ここに若干ながら私立志向の影響がみられる程度です。実質倍率は前年度並みの1.81倍で厳しい入試が続きました。
国際は私立志向の影響を受け応募者が56人の減となり1.85倍まで下がりました。応募倍率が1倍台まで下がったのは20年以上なかったことです。豊多摩や調布北など同じ都立高に移動した可能性もありますが、やはり私立志向の影響を最も受けたと考えられます。併願校としてよく利用される拓殖大学第一や国学院、錦城などの推薦応募者が増えているのでそれらの私立高に向かったのではないでしょうか。
中野区・杉並区・練馬区

この地域の最終応募者数は前年度より297人、8.1%の減で私立志向の影響を受けた地域といえます。西を筆頭に井草、練馬、光丘は最近の5年間でもっとも少ない応募者数になり、倍率アップしたのは豊多摩、石神井、大泉桜の3校だけでした。この地域全体の不合格者数は1,012人から777人へ235人23.2%の減。実質倍率も1.44倍から1.34倍に下がり全体的に緩和されました。
西は進学指導重点校の中で青山とともに私立志向の影響を受けた学校といえます。今年度の応募者数は前年度より21人少ない407人でしたが、この応募者数は最近の5年間でもっとも少ない人数です。加えて受検棄権者が60人から76人とこの5年間でもっとも多く、棄権率も14.0%から18.7%にアップしました。その結果、実質倍率は1.2倍台まで下がり、近年でもっとも緩やかな入試になりました。私立志向の高い地元杉並区や世田谷区、武蔵野市などからの入学生が多いことが応募減、棄権者増の要因となったようです。
逆に豊多摩は67人の応募増となり倍率は2倍を超えました。募集人員の2倍以上の応募者数を集めたのは3年ぶりのことです。国際や駒場からの移動があったのかもしれません。もともと人気の高い学校ですが、受検棄権率が10%を超えるなど私立志向の影響を受けやすい位置にありました。しかし今年度は人気の方が勝ったようです。また併願校としてよく利用されていた東京農業大学第一が高校募集停止になったことも応募増の要因になったのかもしれません。この結果、不合格者数は200人を超え(223人)、受検生の4割以上が不合格になる激戦でした。ここまで厳しい入試になると来春の入試では敬遠され倍率ダウンになる可能性が高いと見込まれます。
井草は校則や制服がなく自由な校風で昔ながらの都立高といえます。それが受け入れられているのか人気も高く高倍率入試が続いていました。しかし今年度は応募者が104人の大幅減となり、倍率も1.4倍台まで下がりました。応募者数318人は最近の5年間でもっとも少なく、300人台は6年ぶりです。例年の高倍率を敬遠して石神井に移動したとも考えられますが、やはり私立志向の影響も受けたのではないでしょうか。不合格者は前年度(142人)より大幅に減って62人。実質倍率も急落して1.2倍台と本校にしては緩やかな入試になりました。
石神井は応募増です。前年度に112人の減となり、1.7倍と本校としては低い倍率になったことから、今年度は34人増え倍率も1.8倍台にアップしました。前年度に激戦だった井草からの移動があったと思われます。しかし2023年度の485人には程遠く、練馬区の生徒減のほか、私立志向の影響も受けて伸び悩んだのではないでしょうか。不合格者数は146人で受検生の4割が涙をのみましたが、これも本校としては少ない方になります。
武蔵丘は78人の応募減となり、3年ぶりに応募者数が400人を割り込みました。応募者数の増減は大きい方で、最近の5年間では500人近い応募(2023年度の497人)があったかと思えば350人程度で収まった年(2021年度の353人)もあります。その点では今回の391人という人数は本校としては少ない方で、私立志向の影響を受けたといえるかもしれません。校舎の改築工事を予定しており、2026年夏から仮設校舎での生活になる予定で、入試の倍率にも影響を及ぼしそうです。
杉並も変動が大きく、今年度は応募者が105人の大幅減になり、倍率も1.2倍台まで下がりました。受検棄権率も上がり(11.4→13.6%)私立志向の影響を受けたといえます。入学生が地元の杉並区のほか、世田谷区や三鷹市、武蔵野市など私立志向の高い地域が多いためと考えられます。この結果、不合格者が前年度より約100人減って22人となり緩やかな入試になりました。
鷺宮は人気校で高倍率になることが多い学校です。前年度は応募者が大幅減になり、倍率も本校としては低い1.6倍台に下がりました。そして今年度は志願締切時には43人の応募増になったものの、志願変更で抜けて結果的に前年度並みの倍率で留まりました。2022、2023年度の応募者数は400人を超えていたので、やはり私立志向の影響を少なからず受けたのではないかと思われます。
練馬も私立志向の影響を受けたと考えられます。練馬区の生徒数が減少しており、それも関係しているかもしれませんが、今年度の応募者数は近年にない少ない数になっているうえ、棄権率もアップした(2.4→6.2%)からです。この結果、不合格者は4人のみで緩やかな入試になりました。
光丘も最近の5年間でもっとも少ない応募者数で、倍率は0.7倍台まで落ち込みました。棄権率も7.5%から10.1%に上がり私立志向の影響が現れています。5年以上、受検生全員合格の状態が続いており、今年度は67人の募集数で第二次募集を実施。さらに33人の募集数で第三次募集を実施しました。
田柄は通信制志向の影響を受けており、この5年間、応募者数が募集人員より少ない状況が続いています。今年度は応募減になったものの微減でとどまり、0.8倍台を維持しましたが、受検棄権者が7人から12人に増え私立志向の影響も受けました。
大泉桜は広報活動の成果か2年連続で応募増となり、今年度の応募者数は6学級募集時代の2019年度と同じ190人台まで増えました。その結果、不合格者は前年度(9人)の約3倍25人に増えています。練馬区の生徒減や私立志向の逆風を受けながら健闘した学校の一つです。